人類の歴史において、芸術の「生」と「死」をめぐる問題は、つねに活発な議論の渦中におかれてきました。一体、どのような状況をもってすれば、絵画や建造物は「生きている」と言えるのでしょうか?また、その「死」とは、一体何を意味するのでしょう? 近現代絵画の複雑な組成に目を凝らすこと、建造物の復元や修理の射程をひもとくこと、失われた記憶を再構築し新たな造形を生みだすこと──本シンポジウムでは、これらの領域に携わる人々が一堂に会し、それぞれの視点を共有しながら、芸術作品の保存や延命の多様な可能性と意義について再考します。各々のいとなみは異なる前提を持ちますが、いずれもが芸術が持つ「記憶」と「未来」、そして「生と死」の意味を問う使命をたずさえています。登壇者には、国内外で活躍するアーティストの竹村京、歴史的建造物の保存を専門とする青柳憲昌、そしてアンゼルム・キーファーの仕事に精通する美術史家ガブリエレ・グエルチョを迎えます。専門の異なる彼らが交差することで、変化と普遍、修復と保存、記憶と創造の境界に新たな光が当てられることでしょう。
この取り組みは、美術作品の保存や修復業務に携わりながら、保存修復学を理論的に研究している田口かおり(京都大学)と、領域横断的な芸術の継承をもとに新たな表現へとつなぐ、クリエイティヴ・アーカイヴを推進している平諭一郎(東京藝術大学)の共同企画です。今後も継続的に、芸術の時間性や再現性を問い直す活動を続けてまいります。
日 時:2025年3月29日(土)14:00-17:30
場 所:京都大学 人間・環境学研究棟 地下大講義室
言 語:日本語(一部イタリア語)
主 催:京都大学人間・環境学研究科田口かおり研究室、東京藝術大学未来創造継承センター
助 成:JSPS科研費24K03506、23K00189
参加方法:以下のお申込みフォームから参加登録をお願いいたします。(定員に達し次第、締切ります)
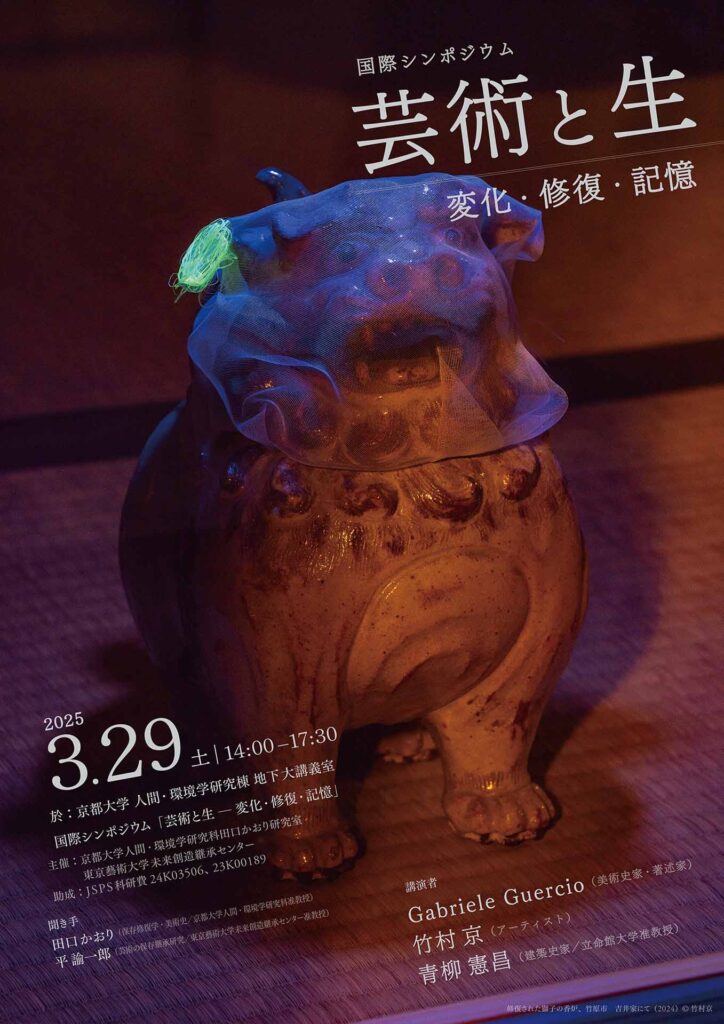
講 演:Gabriele Guercio(美術史家・著述家)
「芸術作品は死に打ち勝つのか?」
イタリアのミラノを拠点に活躍。専門は近現代美術史、美術理論史、美学・哲学。これまで、ローマ大学やナポリ大学で教鞭をとり、ワシントン・ナショナル・ギャラリーの視覚芸術高等研究センターでフェローとして活動。J. P. ゲティ美術・人文学ポストドクトラル・フェローシップを受賞。著書や編著に、『存在としての芸術:芸術家列伝とその企て (Art as Existence: The Artist’s Monograph and Its Project)』(MIT Press 2006)、『ザ・グレート・サブトラクションThe Great Subtraction)』(ASA Publishers 2011)、『芸術は進化しない—ジーノ・デ・ドミニチスの不動の宇宙 (L’arte non evolve. L’universo immobile di Gino De Dominicis)』(Johan & Levi 2015)、『ピカソの悪魔—一般的創造性と創造の絶対(Il demone di Picasso. Creatività generica e assoluto della creazione)』(Quodlibet 2017)、『芸術作品と新たな起源(Opere d’arte e nuovi inizi)』(Quodlibet 2021)、『ジーノ・デ・ドミニチス読解 (Gino De Dominicis. A Reader)』(Walther König 2024)など。新刊『芸術あるいは衰退——愛好家、専門家、名匠 (Arte o decadenza. Dilettanti, professionisti, maestri)』(Quodlibet 2025)が本年2月に刊行されたばかりである。
講 演:竹村京(アーティスト)
「修復・何を直そうとしているのか?」
1975年東京生まれ、東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。同大学大学院美術研究科修了後、ドイツ・ベルリンでの留学を経て滞在。現在は高崎で制作活動を行なっている。刺繍という行為は、竹村にとって「仮に」という状態を作り出すことを意図しており、失われてしまったものや記憶のかけらをより具体的な存在へと昇華させる。
主な個展として、「親愛なるあなたのために」タカ・イシイギャラリー(東京、2004年)。「Kei Takemura」ギャラリー・アレクサンドラ・サヘブ(ベルリン、2004年)、「はなれても」タカ・イシイギャラリー(東京、2007年)、「A part Apart」トーキョーワンダーサイト(東京、2008年)、「見知らぬあなたへ」タカ・イシイギャラリー(東京、2012年)、「なんか空から降ってくるよ」タカ・イシイギャラリー(東京、2016年)、「Madeleine. V, Olympic, and my Garden」タカ・イシイギャラリー(東京、2019年)など。「第15回シドニー・ビエンナーレ」(2005年)、「横浜トリエンナーレ」(2020年)に参加するなど、国際的に高い評価を獲得しながら活動の場を広げている。
講 演:青柳憲昌(建築史家)
「「復元」による建築の転生:文化的記憶の再帰性・再現性」
立命館大学准教授。2008年、東京工業大学にて日本近代の文化財保存史研究で博士号(工学)を取得。東京工業大学助教を経て、2013年より立命館大学で教鞭を執る。日本建築史、文化財保存史をはじめ、復元建築や歴史都市防災などに関する広範な研究活動を展開し、日本の建築文化継承のために関西を中心に歴史的建築の保存活動・フィールドワークに数多く関わる。2016年より法隆寺金堂壁画保存活用委員会専門委員(アーカイブWG座長)。主著に『建築家による「日本」のディテール』(彰国社、2023)、『日本近代の建築保存方法論』(中央公論美術出版、2019、建築史学会賞受賞)、『建築史家・大岡實の建築──鉄筋コンクリート造による伝統表現の試み』(川崎市立日本民家園、2013、共著、日本建築学会著作賞受賞)など。保存改修作品として「西陣寺之内通の町家」(共作、2021)がある。
聞き手:田口かおり(保存修復学・美術史)
京都大学人間・環境学研究科准教授。1981年東京都生まれ。専門は、保存修復理論、保存修復史、美術史、表象文化論など。国内外の美術館にて、近現代美術の保存修復や光学調査、展覧会のコンサベーションを担当。著書に『保存修復の技法と思想―古典芸術・ルネサンス絵画から現代アートまで』(平凡社2015年/平凡社ライブラリー2024年)、『タイムライン─時間に触れるためのいくつかの方法』(this and that 2021年)、『絵画をみる、絵画をなおす 保存修復の世界』(偕成社 2024年)など。4月に絵本『どうやって美術品を守る?保存修復の世界をのぞいてみよう』(作:ファービエンヌ・マイヤー、ジビュレ・ヴルフ 絵:マルティーナ・レイカム、監訳:田口かおり 翻訳:中村智子)を刊行予定(創元社 2025年)。
聞き手:平諭一郎(芸術の保存継承研究)
東京藝術大学未来創造継承センター准教授。1982年福岡県生まれ。専門は文化財・芸術の保存、継承研究。創造の過程や周辺、実践知といった芸術資源から新たな表現を生み出すクリエイティヴなアーカイヴを推進し、研究プロジェクトや展覧会の企画、論考、制作を行う。主な企画に、「芸術の保存・修復―未来への遺産」展(2018年)、「再演―指示とその手順」展(2021年)。また、同展を記録した編著『再演―指示とその手順』を出版(美術出版社 2023年)。芸術保存継承研究会を主宰し、芸術の保存や修復、再現、再演、アーカイヴについて、美術や音楽だけでなく、生命科学、伝統芸能、儀礼などの専門家を招いて、領域横断的に議論する研究会を実施している。
問合せ先:東京藝術大学 未来創造継承センター(担当:平)
future@ml.geidai.ac.jp